アンバンドリングとは?意味・事例・メリットとデメリット、価格戦略の実務ステップを解説-企業成長支援- GDG
MAGAZINEマガジン


アンバンドリング(Unbundling)は、もともと1つのセットとして提供していた商品やサービスを要素ごとに分けて単独で提供する手法です。
本記事では、アンバンドリングの意味からメリット・デメリット、成功事例、導入時の実務ステップまで体系的に解説します。
目次
アンバンドリングとは?
アンバンドリング (Unbundling) とは、ひとつにまとめて提供・販売されていた商品やサービスを分解し、顧客が必要なものだけを選べるようにする販売・提供方法です。顧客の自由度を高め、企業側は価格設定や商品構成の柔軟性を確保できるのが特徴です。
バンドリングとの違い
- バンドリング(バンドル販売)
複数の商品・サービスをセットで販売(例:ソフト+サポート付きパック) - アンバンドリング
セットを分解し、個別に販売(例:ソフト本体とサポートを別料金で提供)
※UnbundlingはIT・通信・金融業界で使用され、消費財・サービス業ではNo-frills, à la carte, optional pricingなどを使用することが多い
クロスセルやプロダクトミックスとの関係
アンバンドリングはこれらと組み合わせることで、商品ラインナップ全体の最適化に役立ちます。
[関連]クロスセル・アップセル・ダウンセルの詳細はこちらから
アンバンドリング戦略のメリット・デメリット
アンバンドリング戦略の導入を検討する際には、企業と顧客双方の視点から、メリットとデメリットを冷静に評価する必要があります。
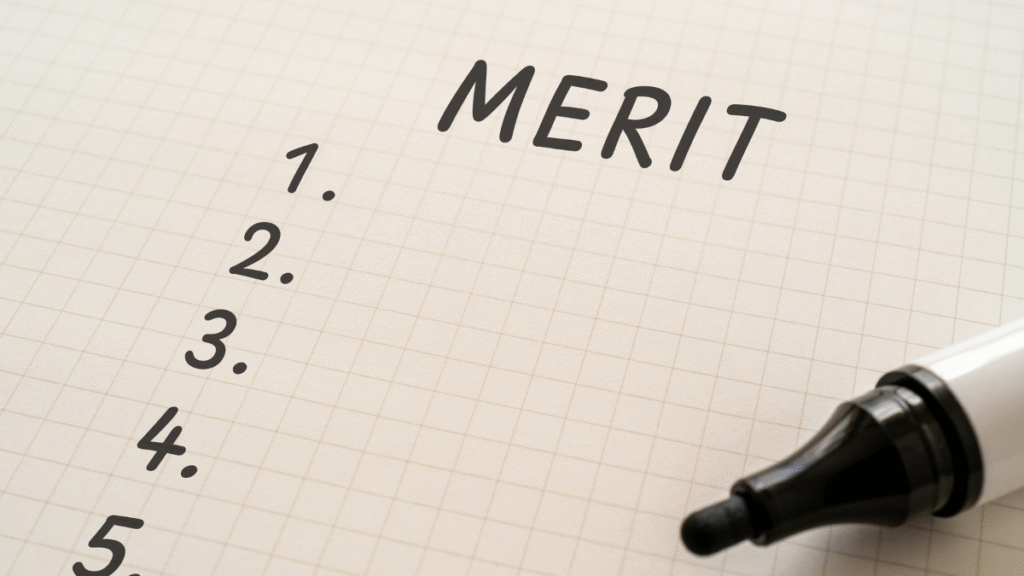
顧客側のメリット
- 「必要なものだけ」を選べる自由
必要な機能やサービスだけを選んで対価を支払うため、不要なコストを削減できます。 - 小規模での導入が可能(低リスク)
高額なフルパッケージを避け、低コストで試せるため導入のハードルが下がります。特に中小企業や個人事業主にとって、リスクを抑えられるメリットは大きいでしょう。 - 機能が絞られたシンプルな利用体験
機能が絞られている分、操作が直感的でわかりやすく、多機能で複雑なサービスよりも快適な体験につながることが多くあります。
顧客側のデメリット
- 選択肢が多く混乱する可能性
選択肢が多すぎると、どれが最適か判断する負担が増し、かえって混乱を招く「選択のパラドックス」に陥りがちです。 - 単品追加で割高になるケース
必要な機能を一つひとつ追加していくと、結果的にセットプランよりも高額になる可能性があります。 - サービス連携の手間や知識が必要
複数のサービスを組み合わせる場合、データ連携や設定は顧客自身の負担となり、時間や専門知識が求められます。
企業側のメリット
- 新規顧客層へのアクセス拡大
これまで価格や機能の多さで購入をためらっていた層に対し、必要な機能だけを安価に提供することで、新たな顧客層へのアプローチが可能になります。 - アップセル/クロスセルによる収益拡大
まずは手頃な基本機能で顧客を惹きつけ、付加価値の高いオプションを追加提案することで、さらなる収益機会を創出します。 - 大手に対抗する差別化手段
特に新規参入企業が、既存大手の包括的なサービスに対抗する上では、強力な武器となり得ます。
企業側のデメリットとリスク
- 収益の共食い (カニバリゼーション) と利益率低下
既存顧客が安価なプランに乗り換えることで、全体の利益率が低下する恐れがあります。緻密な価格戦略が不可欠です。 - 商品・価格管理の複雑化
商品ラインナップや価格帯が増えることで、マーケティングや顧客管理のオペレーションが複雑化します。 - 顧客関係の希薄化
顧客が一部の機能しか利用しない場合、接点が減少し、関係性が希薄になるリスクがあります。
成功条件
これらのメリット・デメリットはトレードオフの関係にあります。「新たな顧客層へのアプローチ」は、「カニバリゼーション」と、「選択の自由」という価値提供は、「選択の複雑さ」を生む可能性があります。
したがって、アンバンドリング戦略の成功とは、顧客を混乱させない絶妙な選択肢の設計と、初期の利益減を補って余りある魅力的なアップセル戦略を両立させることに他なりません。単なるサービスの「分解」ではなく、高度なバランス感覚が求められる経営判断です。
アンバンドリングを採用した企業事例
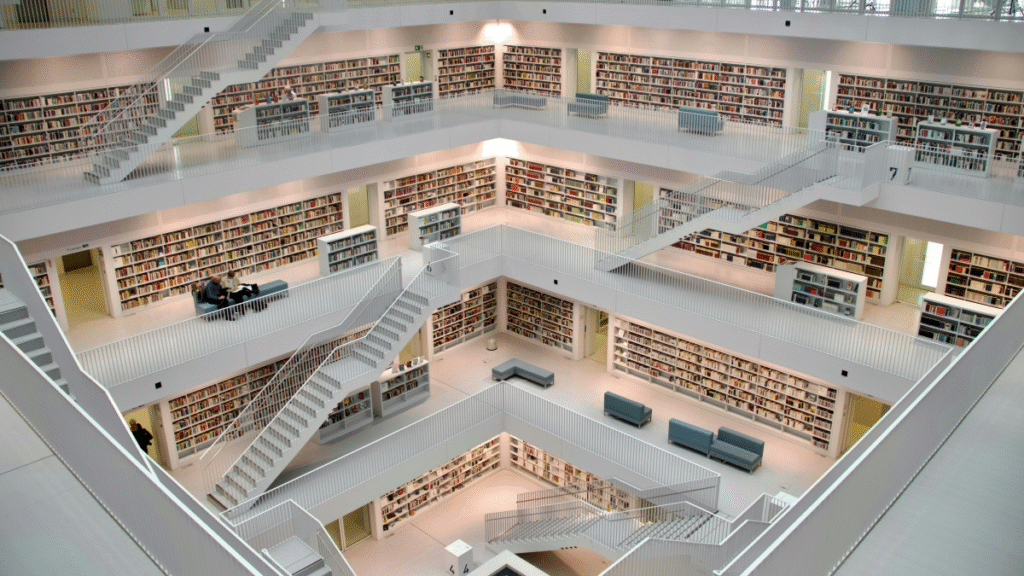
以下ではアンバンドリングの具体的な事例を紹介します。
SaaS業界:ソフトウェア機能のモジュール販売
現代のソフトウェア(SaaS)ビジネスにおいて、アンバンドリングは基本的な戦略となっています。かつて統合パッケージとして販売されていたソフトウェアが、現在では「顧客管理」「マーケティング支援」「データ分析」といった機能単位(モジュール)で提供されるのが一般的です。
これにより、まず必要な最小機能から低コストで導入し、事業の成長に合わせて機能を追加していくことができます。提供側は、利用データに基づき、最適なタイミングで関連機能を提案(クロスセル)することで、顧客のLTV(生涯価値)を最大化しています。
通信業界:「端末と通信のセット」という常識を分解
かつて「実質0円」といった形で、端末代金と通信料金が一体化(バンドル)していた携帯電話契約ですが、「分離プラン」の導入で、この常識は大きく変わりました。
端末は端末、通信は通信として価格が明確に分離(アンバンドル)されたのです。これにより、利用者は自由に通信会社を選び(SIMのみ契約)、好きな端末を別途購入するといった、より柔軟な選択肢を手に入れました。この変革は、料金体系の透明性を高め、市場の競争を活性化させる大きなきっかけとなりました。
LCC:「至れり尽くせり」な航空券を分解
「空の移動」というコアな価値だけを切り出し、それ以外を徹底的にオプション化したのが格安航空会社(LCC)のビジネスモデルです。(アンバンドリングより、ノーフリルズと呼ばれます。)
従来の航空会社では当たり前だった手荷物の預け入れ、機内での食事、座席の指定といったサービスは、すべて追加料金が必要なオプションとして提供されます。これにより、「移動さえできれば良い」と考える乗客は圧倒的な低価格を享受でき、「快適さも欲しい」と考える乗客は必要な分だけサービスを購入できます。航空券という商品をアンバンドリングし、顧客自身が価値を再設計できるようにした画期的な事例です。
小売業界:ローソンストア100「100円おせち」
高価で量が多いセット販売が主流だった「おせち料理」。この常識に切り込んだのが、ローソンストア100の「100円おせち」です。
伊達巻やかまぼこなどを一品100円で個別に販売することで、「一人暮らしで少しだけ食べたい」「好きなものだけを詰め合わせたい」といった、これまで見過ごされてきた潜在ニーズを掘り起こしました。
この戦略は、売れ筋商品をデータで可視化し、翌年の商品開発に活かすという副次的なメリットも生み出しています。
美容・サービス業界:QBハウスの「カット専門」モデル
「10分の身だしなみ」をコンセプトに掲げるQBハウスは、従来の理美容サービスを大胆にアンバンドリングしたパイオニアです。
一般的な理容室が提供するシャンプーやブロー、マッサージといったサービスをすべて削ぎ落とし、「ヘアカット」という中核機能に特化。これにより、短時間・低価格を実現し、多忙なビジネスパーソンなど「時間効率」を重視する新たな顧客層の支持を集めました。サービスを分解することで、高回転率という独自の収益モデルを確立した事例です。
アンバンドリング戦略の活用ポイント
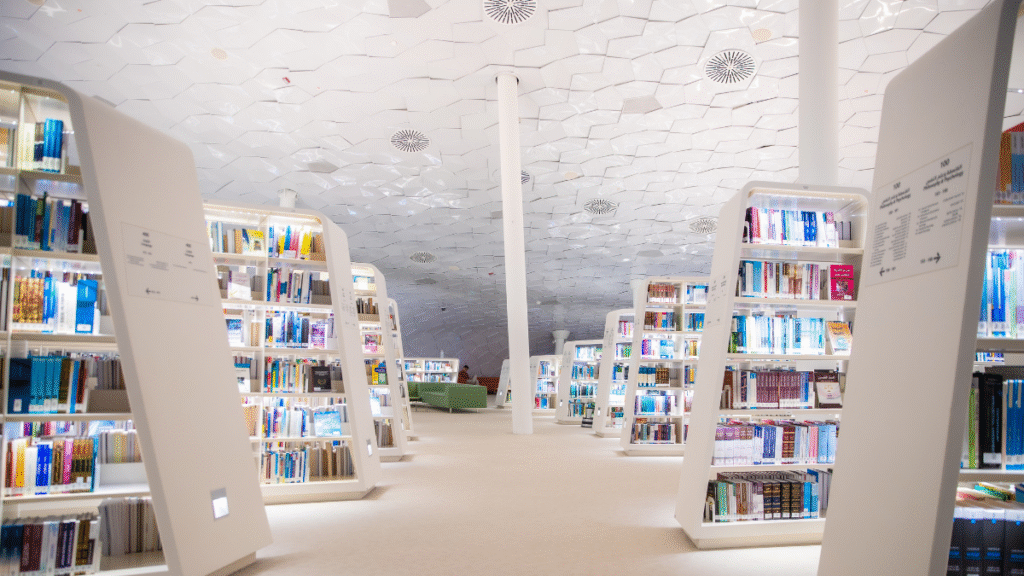
適用が有効な条件(業界・市場状況)
アンバンドリングは、すべての業界・商品に万能ではありません。以下の条件が揃うと効果を発揮しやすくなります。
- 顧客の「これで十分」という声が大きい
市場に「多機能よりシンプルさ」「高品質より低価格」を求める層が確実に存在するなら、機能を絞った廉価版の提供は有効です。格安航空会社(LCC)や通信業界のSIM単体契約などが典型例です。 - 顧客の「欲しいもの」がバラバラである
全員が同じものを欲しがるのではなく、顧客によって必要な機能やサービスレベルが大きく異なる市場。このような状況で画一的なパッケージを提供すると、多くの人にとって「帯に短し襷に長し」となります。個々のニーズに応える「アラカルト方式」が顧客満足度を高めます。 - サービスの価値を「松・竹・梅」に分解できる
提供するサービスの中に、コストが大きくかかる部分とそうでない部分が明確に分かれている場合、高コストな要素をオプションとして切り離すことで、柔軟な価格設定と緻密なコスト管理が両立できます。 - 「高くて手が出ない」潜在顧客がいる
フルパッケージの価格が参入障壁となり、興味はあるものの購入をためらう見込み客がいる市場。この場合、機能を絞った安価な「お試し版」や「エントリーモデル」を用意することで、新たな市場を開くことができます。 - 規制や市場慣行の変化:
法改正や業界全体の慣行見直しにより、価格の透明性やサービスの個別提供が求められるようになったタイミングは、アンバンドリングを導入する絶好の機会と言えます。
バンドリングとの使い分け
アンバンドリングとバンドリングは、二者択一ではなく状況に応じて使い分ける戦略です。
バンドリングが有効な場合
- 「セットでお得」が響く市場:
遊園地のフリーパスやリゾートホテルの宿泊プランのように、顧客が個別に選ぶ手間を省き、お得感や網羅性を求めている場合。 - 提供側に規模の経済が働く場合:
一括で提供することでオペレーションコストを削減でき、その分を価格や利便性で顧客に還元できる場合。 - 販売促進や在庫管理が目的の場合:
人気商品と他の商品を組み合わせることで、クロスセルを促進したり、在庫の回転率を上げたりしたい戦略的な意図があるとき。
アンバンドリングが有効な場合
- 「自分仕様」を求める顧客に応える:
顧客のニーズが多様化し、不要な機能やサービスにお金を払いたくないという傾向が強い場合。 - 価格への納得感を醸成したい:
価格の内訳をガラス張りにすることで、顧客の信頼を得て、長期的な関係を築きたい場合。 - 段階的な収益モデルを構築したい:
まずは安価な基本機能で顧客を獲得し、付加価値の高いオプションでLTV(顧客生涯価値)を高めていく戦略を描ける場合。
実務上、多くの成功事例では両者を巧みに組み合わせています。 「核となる価値」はセット(バンドル)で提供し、顧客の好みが分かれる「付加価値」は選択式(アンバンドル)にするというハイブリッド戦略です。例えば、PCのOSのように基本的な機能はバンドルしつつ、専門的なソフトウェアはアンバンドルで提供する形がこれにあたります。
成功・失敗事例の共通点
成功事例の共通点
- 「守るべき価値」と「切り離せる付加価値」を見極めている
成功企業は、自社ブランドの根幹をなす体験や品質は決して分解しません。あくまで「なくても本質は損なわれないが、あればもっと便利になる」という周辺サービスを切り離すことで、コアな魅力を維持しています。 - 追加オプションが「明朗会計」である
それぞれのオプションが「何をしてくれるのか」「なぜこの価格なのか」が、顧客にとって一目瞭然です。価値が不明瞭なオプションはなく、利用者は納得して追加購入できるため、満足度が高まります。 - 「選択の自由」と「選びやすさ」を両立させている
ただ選択肢を並べるだけでなく、「迷ったらコレ」という推奨プランや、「セットにするとお得」といったパッケージを提示。顧客が選択肢の海で溺れてしまわないよう、購入までの道のりを巧みにガイドしています。 - データに基づき、常に戦略を微調整している
オプションの選択率(付帯率)や顧客単価、解約率といった重要指標(KPI)を常に観測しています。どのオプションが響いているのか、価格設定は適切かをデータで判断し、戦略を柔軟にアップデートし続けています。
失敗事例の共通点
- 分解してはいけない「コア」まで分解してしまった
コスト削減を追求するあまり、ブランドの根幹をなす体験や品質までオプション化。
結果としてサービスの魅力そのものが失われ、顧客にとって「安かろう悪かろう」の印象だけが残ってしまいます。 - 選択肢が多すぎて、顧客を戸惑わせてしまった
良かれと思って用意した多くのオプションが、逆に顧客の負担に。価格体系が複雑になりすぎ、利用者は「どれを選べばいいかわからない」と感じ、検討すること自体を諦めてしまいます。 - 社内のオペレーションが破綻し、収益性が悪化する
増えすぎた商品プランや価格帯の管理が煩雑になり、現場が混乱。適切な価格改定やキャンペーンの管理ができなくなり、結果として収益性が低下するという状態に陥ります。 - 長年のファン(既存顧客)への配慮を欠いてしまう
新しい料金体系への移行について、既存顧客への丁寧な説明を怠った結果、「実質的な値上げだ」「サービスが悪くなった」といった不満が噴出。ロイヤリティの高い優良顧客の離反という、最も避けたい事態を招きます。
価格アンバンドリングの実務ステップ

アンバンドリング戦略は、緻密な価格設定にかかっています。ここでは価格を設計・検証していくための実務プロセス例を解説します。
フェーズ1:価格戦略の基礎固め
検証可能な価格フレームをあらかじめ設計します。
1. 提供価値とコスト構造の分解
サービスを要素(機能、サポート、リソースなど)に分けます。
それぞれにかかるコストと、顧客にもたらす効果(時間短縮、売上増など)をセットで整理します。
2. プライシング構造の設計
分解した要素を再構成し、顧客に提示する価格構造を組み立てます。
- 標準プラン:誰もが使う基本機能
- オプション:追加できる機能
- 課金の基準(ID数、データ量など)
- 比較しやすい段階構造(松竹梅型)
3. 価格運用のガイドライン策定
価格体系に一貫性を持たせるため、運用ルールを明文化します。
- 最低ライン:必要な利益を守る金額
- 最高ライン:顧客が払ってもいいと思える金額
- 端数価格の使い方(例:9,800円)
- 上位プランやオプションの組み合わせで損をしないようにするルール
4. 初期価格レンジの仮設定
競合の価格や顧客の支払意欲を調べて、複数の候補を設定します。事業目標に合うかもチェック。
フェーズ2:市場データを活用した価格改善サイクル
価格は固定せず、実データを基に継続的に最適化します。
1. 検証シナリオと評価指標の設定
「新価格プランAは、顧客単価を15%向上させるが、コンバージョン率は5%低下するにとどまる」といった具体的な仮説を構築します。同時に、仮説の成否を客観的に判断するための主要業績評価指標(KPI)、例えば顧客生涯価値(LTV)や顧客獲得コスト(CAC)回収期間などを定義します。
2. 検証方法の選定
仮説を検証するためのテスト手法を選択します。
- A/Bテスト:価格を変えて比較検証。
- コンジョイント分析:機能と価格の組み合わせに対する顧客嗜好を数値化。
期間・サンプル数・有意水準も事前に設定します。
3. データ分析と意思決定(Go/Hold/Pivot)
一定期間のテストで収集したデータを分析し、仮説が正しかったかを評価します。重要なのは、短期的な売上変動だけでなく、解約率やアップセル率といった中長期的な指標への影響も考慮に入れることです。データに基づき、新価格を本格導入するか、再度仮説を練り直すかの意思決定を行います。
- Go:想定KPI達成
- Hold:追加データ収集や条件調整
- Pivot:課金軸やティア構造の修正
4. 段階的導入と社内展開
一斉導入は避け、セグメントや地域単位で段階的に展開。KPIを週次でモニタリングし、必要に応じて即時修正。営業・サポート部門には新価格の背景やトークを共有し、移行を円滑化します。
アンバンドルを有効活用するために

アンバンドルは売上拡大の有力な手段ですが、その実施には緻密な計画と検証が求められます。
メリットを最大限享受しつつリスクを最小化できれば、自社の競争優位性向上にもつながります。
さらなる企業成長のためには営業戦略と経営管理体制の構築が必要です。ぜひグランド・デザイニング・グループにご相談ください。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
まずは無料相談してみる参考文献・出典:
[1] 総務省「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」
[2] 経済産業省「令和3年度 電子商取引に関する市場調査報告書」
▼「GDGマガジン」とは?
GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。
著者:GDGマガジン編集部
(グランド・デザイニング・グループ)
※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。
関連記事
 マガジンTOP
マガジンTOP



