持株会社を活用した事業承継。流れ、メリット・デメリットを解説-企業成長支援- GDG
MAGAZINEマガジン

事業承継において株式の取り扱いは、重要性が高く、関心事にもなりやすいテーマです。中堅・中小企業の事業承継において、持株会社の活用を検討するケースは多くあります。本記事では、持株会社の概要から、スキーム、メリットとデメリットなどを解説します。
事業承継の全体像については、事業承継ガイドをご参照ください。
持株会社の概要

持株会社とは
持株会社とは、他の会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社のことを指します。持株会社には、事業持株会社と純粋持株会社があり、事業持株会社は、事業を行うかたわらで他の会社の株式を保有する会社、純粋持株会社は、事業を行わずに、純粋に他の会社の株式を保有する会社です。
持株会社への移行事例
上場会社でも、経営の監督機能強化や、迅速な意思決定などのコーポレートガバナンスの強化や、M&Aなどを通じたグループ経営の加速などのために、持株会社への移行は多くみられます。持株会社への移行は、『ホールディングス化』とも呼ばれ、代表的な企業としては、日清食品ホールディングス(日清食品㈱、明星食品㈱など)、J. フロント リテイリング(㈱大丸松坂屋百貨店、㈱パルコなど)、ニトリホールディングス(㈱ニトリ、㈱島忠など)などが挙げられます。
事業承継における持株会社スキームの活用
持株会社の活用パターン
事業承継における持株会社の活用には大きく2パターンあります。
① 後継者による持株会社の設立と株式取得
後継者が持株会社を新設し、持株会社にて借入金等により資金調達を行います。
その後、現経営者が保有する会社株式(以下、対象会社)を持株会社にて取得します。
対象会社からの配当を通じて、借入金等を返済していきます。

② 株式移転等による持株会社の設立
持株会社は、株式移転、株式交換、会社分割などによっても設立が可能です。株式移転では、現経営者が保有する対象会社株式は持株会社に移転し、株主に対しては持株会社の新株を割り当てます。 税制適格要件を満たせば、適格株式移転となります。なお、持株会社の設立時点では、後継者への株式の承継は完了していませんので、その後に贈与・相続などで承継を行うことになります。
従業員承継(MBO)での活用も可能
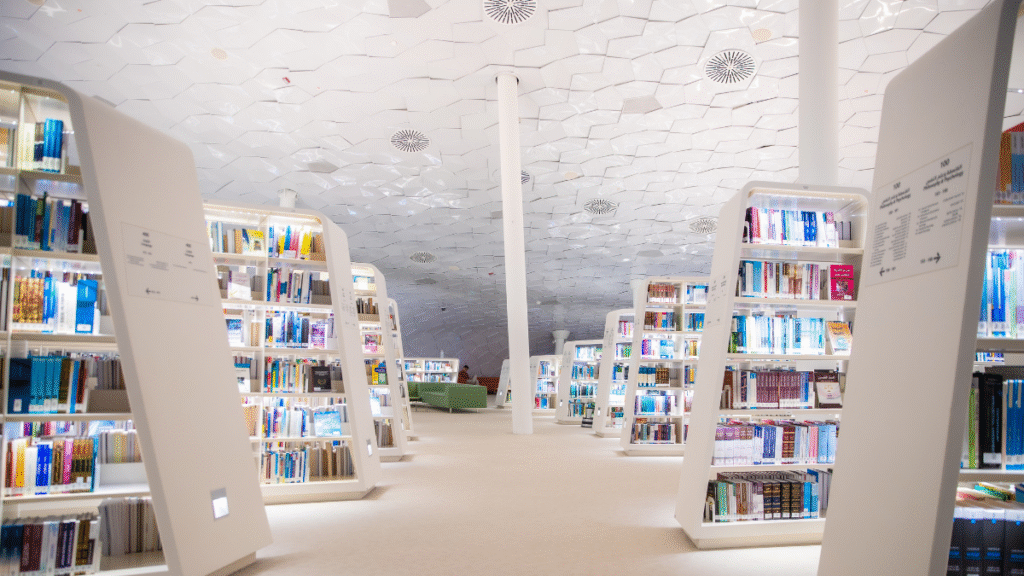
親族内での後継者不在課題がある現況では、マネジメント・バイアウト(MBO)、つまり従業員承継においても持株会社の活用が可能です。従業員承継が株式の譲渡(売買)によって行われる場合、譲渡(売買)の場合には、多額の資金が必要となることも少なくありません。
株式の所有と経営を別ける、つまり、経営のみを役職員へ承継し、株式はファミリーオフィスのように創業家が持ち続けるという方法も考えらえますが、非上場の場合に、経営者のコミットメントをいかに引き出すかや、必要なガバナンスを利かせられるか(単なる計数管理ではなく)という課題が残ります。この点、後継者が経営面での承継とともに株式を取得することで、所有と経営の一体構造を築き上げられるという点においては、持株会社による従業員承継は現実的な選択肢となり得ます。以降は、『持株会社を活用した株式取得と事業承継』について、メリットとデメリットを見ていきます。
[関連]従業員承継の概要と実行ステップ
持株会社のメリット

現在の経営者利潤の確保
現在の経営者が、経営者利潤としての現金を確保できます。株式の譲渡益は課税対象となりますが、役員報酬や配当による現金確保と比べると、分離課税となるため税率が有利になる可能性があります。
現在の経営者による現金の確保(相続の観点)
現在の経営者は、将来の相続を見据えた納税資金として、現金の確保が可能です。株式のまま相続になると、遺産分割が偏り、遺留分の侵害などのトラブルや、場合によっては財産返還請求により自社株の分散に繋がるリスクがありますが、相続財産を現金としておくと、財産はシンプルな状態になります。
遺留分(相続の観点)
上記と類似しますが、高い評価額の株式を「相続や贈与」で承継した場合、後継者以外の遺留分を侵害することがあります。持株会社の場合、後継者が「買い取り」を行うため、その他の相続人との関係上、有効な施策となる可能性があります。
株式分散リスク回避(経営リスクの観点)
上記に加えて、持株会社が、対象会社の発行済株式のすべてを取得することで、基本的には議決権を集約できます。また、議決権制限株式などを併用すれば、現在の経営者によるガバナンスを利かせたまま、株式については先立って承継を行うなどの工夫も可能です。
資金調達が行いやすい
持株会社では、調達した借入金の返済原資として配当を活用します。「配当金の益金不算入制度」の要件を充足すれば、持株会社が支払を受ける配当金は、そのまま返済原資になります。そのため、配当金および株式取得価額の水準次第では、借入金を弁済する蓋然性が見込めるため、資金調達が可能になります。
仮に個人で対象会社の株式を取得する場合、配当と役員報酬が借入金の返済原資になりますが、個人が受け取る非上場株式の配当は総合課税の対象です。また、役員報酬も課税対象です。つまり、返済原資となるのは、「税引後の」配当と役員報酬です。
株価への影響(37%控除)
純資産価額方式においては、評価通達に基づいて算出した『時価純資産差額』と評価の基となる『簿価純資産価額』との差額、つまり株式の「異動後」に生じた株式の含み益を37%控除できる可能性があります。これについては、親族内承継においても、株価の上昇局面において有利に働く可能性があります。
一方で、後述の通り、持株会社が『株式等保有特定会社』に該当する可能性があるため、いかなる状況でもメリットになるわけでは無いことに注意が必要です。※税理士にご確認ください。
持株会社のデメリット
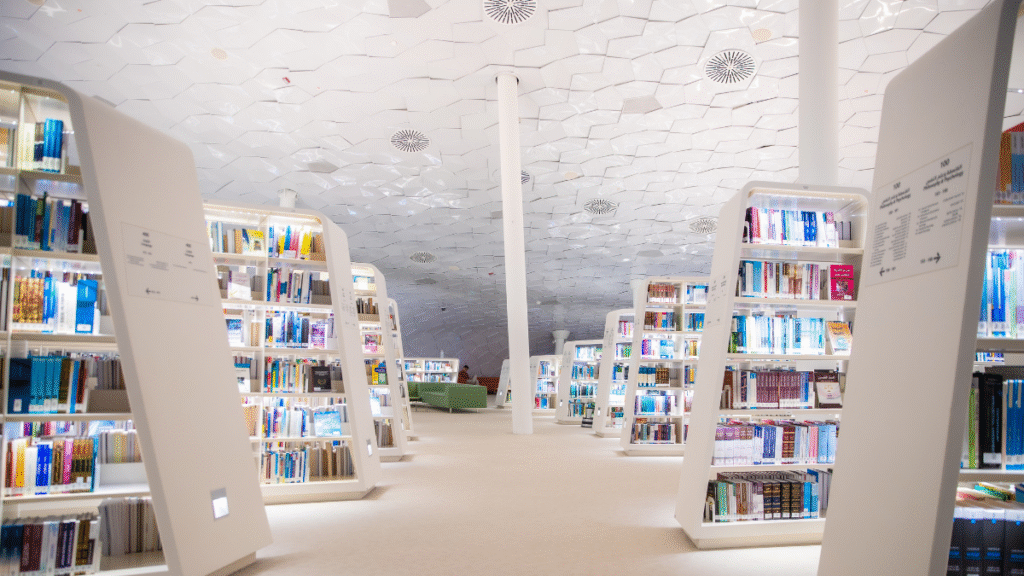
取引する株価と税務リスクの検討
売買のため、相続税評価額ではなく、所得税法上・法人税法上の時価になります。基本的には株式取得価額(買取負担額)が上がる可能性があります(そうでない場合、みなし贈与や受贈益などの認定リスクに留意が必要です)。従業員承継でも、この点には留意が必要といえます。特に親族内承継の場合は、その他の選択肢との比較検討が必要です。
借入金の返済と利息の支払い原資が必要
上述の通り、持株会社の借入金は、配当をもとに返済することがメインです。配当は会社法上、『分配可能額』に制限されるため、会社で利益が出せなければ配当を支払うことは難しくなり、期日設定されている借入金の返済や利息支払いは困難です。借入金返済額や利息などの水準と、利益見通しを踏まえた『事業計画』の作成と検討が必要です。
持株会社の設立や運営に関する事務負担と費用
持株会社の設立や運営に関する事務負担と費用が発生します。
株式の譲渡所得課税が生じる
先述の通り、譲渡所得課税が発生します。
株式とは異なる相続税
現経営者が受け取った現金(相続財産)に、相続時の優遇規程はありません。すべて使い切らない場合、相続財産としては、現金が増えることになります。
持株会社の活用の前に検討を
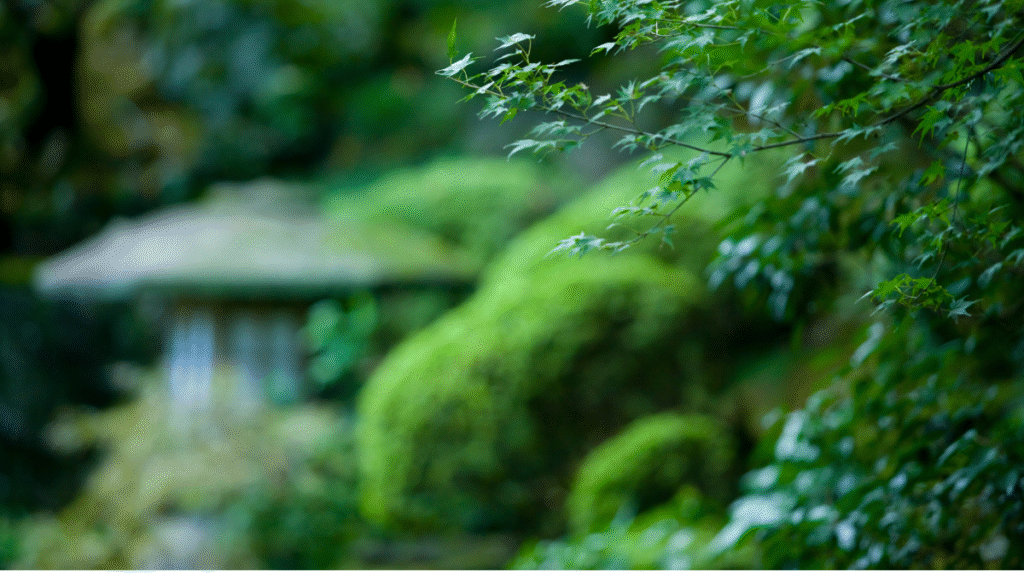
遺留分に関する民法の特例制度
『遺留分に関する民法特例』という制度があります。相続(贈与)で引き継ぐ自社の株式が、遺留分を算定する『遺留分算定基礎算定財産』から除外される(算定に含み入れない)合意(『除外合意』)と、
相続(贈与)で引き継いだ自社の株式を、合意時点での時価評価額で固定する(固定合意)があります(身内で合意すれば良いわけではなく、税理士や弁護士等の証明が必要な点に注意が必要です)。このような制度を活用することが可能なため、遺留分への対応のために、必ず売買が必要なわけではありません。
事業承継税制は親族外でも活用が可能
事業承継税制は、贈与または相続によって株式が承継される場合に、相続税・贈与税の納税を猶予および免除される制度です。様々な理由から、贈与は親族外ではとりづらい選択肢かもしれませんが、制度上は親族外も活用可能となっています。一般的な持株会社スキームは、創業者による株式の売却(株式譲渡)であり、創業者はその対価として現金を受け取ります。この取引には譲渡所得税が課されます。
株式等保有特定会社について
持株会社の総資産(相続税評価)に占める株式等の割合が50%を超えた場合は、基本的に『株式等保有特定会社』に該当します。持株会社の場合、該当する可能性が高いと考えられますが、該当した場合には、株式の評価方法が変わることになるため、その影響を含めた長期的な目線での検討が必要です。
論点が多岐に渡る事業承継に対応するために

事業承継に際する持株会社を活用した株式の承継方法をまとめました。持株会社を活用する場合には、税理士を交えた計画的かつ慎重な検討が重要です。また、メリットとデメリットで見た通り、各ポイントが相互に影響するうえ、主体者・時期・基準によっても、どれが最適な選択肢かが変わってしまうこともあります。また、『株式の取り扱い』は重要ですが、事業承継においてはあくまでも一つの要素にすぎません。
お気軽にご相談ください
事業承継や後継者課題でお悩みの場合は、ぜひグランド・デザイニング・グループにご相談ください。事業承継計画の立案から後継者育成まで、事業承継のあらゆるフェーズを包括的にサポートしています。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
グランド・デザイニング・グループの事業承継コンサルティング
▼「GDGマガジン」とは?
GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。
経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。
監修者

宇納 陽一郎
グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営や事業承継の実体験を活かした事業承継支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。
※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。
関連記事
 マガジンTOP
マガジンTOP




