クロスセルとは?ダウンセル・アップセルとの違いから、売上を最大化する営業戦略を徹底解説-企業成長支援- GDG
MAGAZINEマガジン


効果的なクロスセルは売上と利益を向上させる可能性があります。新規顧客獲得コストが高騰する今、既存顧客からの売上を最大化する営業戦略の重要性が増しています。本記事では、クロスセル・アップセル・ダウンセルの基本定義から成功のポイント、失敗例、心理的背景、そして戦略的活用法までを体系的に解説します。
目次
クロスセルとは?

クロスセルとは、顧客が検討・購入した商品やサービスに、関連性・補完性のある別の商品を組み合わせて提案する手法です。たとえば、オフィスチェアの購入者に、姿勢をサポートするクッションやフットレストを案内するようなケースです。
クロスセルの本質的な目的は、顧客のニーズをより広範に満たして満足度を高め、結果として、長期的なLTV (顧客生涯価値) や顧客の平均単価を向上させることです。
ECサイトでは、商品ページに「この商品を購入した人はこんな商品も買っています」と関連商品が表示されることがありますが、これはクロスセルの一種です。また、5,000円以上購入すると送料無料など、追加購入にメリットを付帯させるケースもあります。こうした提案によって顧客が自分で探す手間を省き、必要なものをお得にまとめて購入できるメリットがあります。
アップセルとは?
アップセルとは、顧客が検討している商品よりも、高価格・高機能な上位モデルを提案し、購入単価を上げる販売戦略です。例えば、標準プランのソフトウェアを検討中の顧客に、より多くの機能を備えたプロフェッショナルプランを提案することです。
アップセルの目的は、顧客が抱える課題をより高いレベルで解決し、包括的なソリューションを提供することにあります。単に高額商品を売りつけるのではなく、顧客が得られるメリット (性能向上や長期的なコスト削減など) を明確に伝える必要があります。基本的なニーズが満たされ顧客がベースの商品価値を実感したタイミングで提案することが重要で、時期尚早のアップセル提案はかえって逆効果となりえます。
ダウンセルとは?
ダウンセルとは、価格やスペックがネックで購入をためらう顧客に対し、より安価でベーシックな代替商品を提案する手法です。上位プランや高価格商品の提案に踏み切れない顧客に対して、負担の少ない選択肢を提示し購入のハードルを下げる狙いがあります。
例えば、上級プランに迷う顧客に、入門版を提示することです。
ダウンセルの目的は、価格が障壁となって顧客を失う「機会損失」を防ぎつつ、まずは関係性を構築することです。初回取引は小さくとも、満足していただければ、将来的なアップセルやクロスセルに繋がる可能性があります。ダウンセルによって新規顧客を失わずに済めば、将来的なLTV (顧客生涯価値) 向上のための重要な第一歩となります。
なぜクロスセル営業が必要なのか?
クロスセル・アップセル・ダウンセルを適切に組み合わせた「クロスセル営業」は、短期的な売上増加だけでなく、顧客との関係性を深め、長期的な成長を可能にするエンジンとなる営業戦略です。新規顧客の獲得コストが高騰する市場環境では、顧客一人ひとりから得られる売上と価値を最大化することが企業の持続的成長に直結します。以下、クロスセル戦略が重要視される理由を解説します。
収益性と利益率の向上
優れたクロスセル戦略は、企業の収益性を大きく向上させます。
マッキンゼーの調査によれば、オンライン小売企業の事例では、クロスセル施策によって売上が20%、EBITDA (利益) が30%向上したという成果が報告されています※。これはクロスセルにより顧客一人当たりの購買点数・範囲が広がり、一人の顧客から得られる収益が高まったためです。
また、マーケティングで知られる経験則「1:5の法則」もクロスセルの重要性を裏付けています。新規顧客の獲得コストは既存顧客維持の5倍かかるとされており、この点からも既存顧客への追加提案は効率的な売上拡大策です。既存顧客へのクロスセル・アップセルに注力することは、限られた営業リソースで高い効果を実現する近道ともいえます。
[出所] Targeted online marketing programs boost customer conversion rates
顧客生涯価値 (LTV) の最大化
クロスセルの目的は、一回限りの取引額を増やすこと以上に、顧客生涯価値 (LTV) を向上させる点にあります。LTVとは、一人の顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらすことが予測される利益の累計です。クロスセルはそのLTVを構成する「顧客単価」と「取引継続期間」の両方に、以下を例とする好影響を与えます。
顧客単価の向上
関連商品を同時に購入してもらうことで、平均注文額 (AOV) が上昇します。また、一度の商談で複数の商品・サービスを販売できれば、営業効率も高まります。クロスセルは追加マーケティング費用を相対的に少なくして、売上アップを図れるため、利益率の向上にも繋がります。
取引継続期間の長期化
顧客の多様なニーズに応えることで満足度とロイヤルティが向上します。これにより、顧客が長期間離反せず取引を継続してくれることが期待されます。また、商品・サービス商品によっては、提供範囲が広がるほど、他社に乗り換える理由も少なくなることが期待できます (スイッチングコストの上昇) 。例えば保険業界では、顧客が保有する商品数が増えるほど解約率が低下することが指摘されています※。
[出所] Customer Behavior and Loyalty in Insurance
クロスセル・アップセル・ダウンセルを提案する際のポイント
クロスセル・アップセル・ダウンセルは、顧客の状況に応じて柔軟に使い分けることで相乗効果を発揮します。提案の成否を分けるのは、どの局面でどの手法を選ぶかという見極めです。例えば以下の問いに沿って提案機会を判断することが考えられます。
- 主なニーズは満たされているが、潜在的で未解決のニーズがあるか?
→ クロスセルの機会。現在の商品を使う中で生じる関連ニーズに応えるアイテムを提案し、顧客への提供価値を拡張しましょう。 - 基本ニーズは満たされているが、より上位の価値を提供できるか?
→ アップセルの機会。現行製品より高性能なモデルや上位プランを提案し、顧客により大きなメリット (効率化・高機能化など) を提示しましょう。 - 価格や機能に対して顧客がためらいを感じていないか?
→ ダウンセルの機会。予算やスペックにハードルを感じている場合は、無理に高額商品を売り込まず一段ハードルの低い選択肢を提示しましょう。まずは取引のきっかけを作り、関係構築を優先することが大切です。
このように顧客を中心に据えて、「今この顧客に本当に役立つ提案は何か」を考えることがポイントです。クロスセル・アップセル・ダウンセルはいずれも顧客の状況に合致して初めて効果を発揮するため、的確なニーズ把握と提案タイミングの見極めが不可欠です。
クロスセル・アップセル・ダウンセルの事例
〈クロスセル〉ハーブティー
睡眠ブレンドの定期便訴求に合わせ、はちみつ・茶こし・耐熱マグの同梱したセットを提案。セット価格は単品合計より3〜5%安く設計し、「夜のリラックス」 (仮称) という体験価値で訴求。初回同梱のみ送料無料で配送コストも最適化。レビュー欄に「一緒に買って良かった物」を収集して推薦精度を改善。KPIはセット比率、定期継続率、配送コストおよび注文数。
〈アップセル〉美容サロン
メニューを「ベーシック・スタンダード・プレミアム」の三段階に再編。プレミアムは髪質改善やホームケア付きで体験価値を明確化。価格差は段階的(例:各+20〜30%)に設定し、予約導線ではスタンダードを初期選択に。カウンセリングで髪の悩みを可視化し、上位提案へ。KPIはメニュー構成比、客単価、リピート率。
〈アップセル〉学習塾
通常授業に「直前対策パック」を上位メニューとして用意。模試フィードバック→弱点補強→本番シミュレーションをシラバス化し、保護者面談で学習曲線の見取り図を示す。早期申込には席確保と教材前倒し提供の特典。KPIは上位コース比率、合格実績、紹介率。過度な不安訴求はクレームの元のため、顧客満足の範囲で提案。
〈ダウンセル〉旅館・ホテル
高単価プランで離脱が多い場合、同日の素泊まりスタンダード+朝食オプションを即時提示。チェックイン時に「館内クレジット」「レイトチェックアウト」を追加販売し、体験価値を補完。KPIは空室消化率、ADR (客室平均単価) 、現地追加率。価格帯を下げつつ総収益は確保する設計。
クロスセル・アップセル成功のポイント
どんなに優れた施策でも、進め方を誤れば“押し売り”に見えてしまいます。ここではクロスセル・アップセル提案を顧客にも歓迎される形で進めるためのポイントをまとめます。
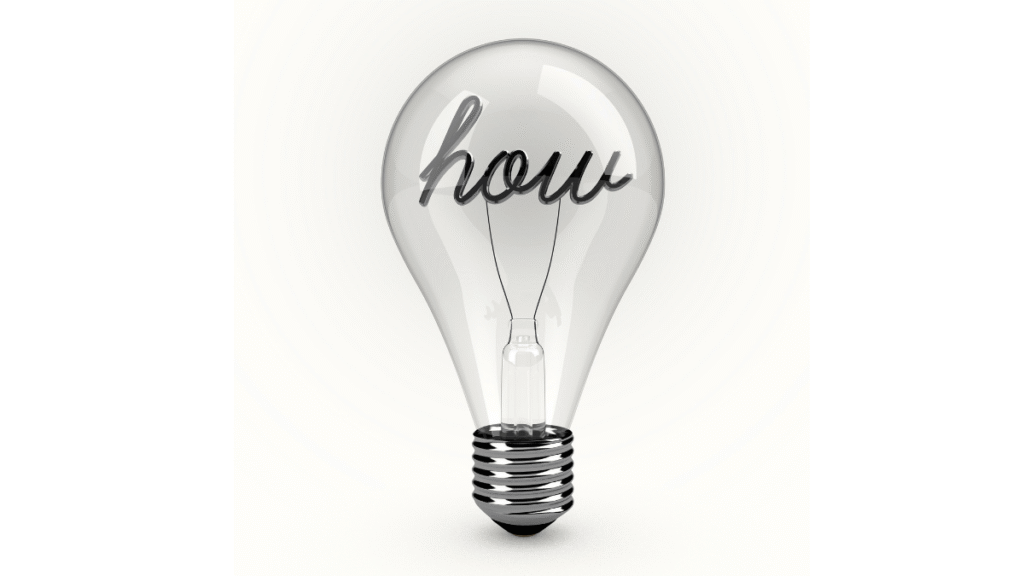
データでニーズを把握する
勘に頼る提案ではなく、データに裏付けられた提案です。分析ツール等を活用し、顧客の購買履歴や行動パターンを継続的に分析し、潜在的なニーズを捉えましょう。根拠のある提案は顧客の信頼を獲得し、成功率を高めます。
タイミングと文脈を見極める
提案のタイミングは内容と同程度、あるいはそれ以上に重要です。現行サービスの価値を実感した後での追加提案は受け入れられやすく、導入効果が見えない段階での上位プラン提案は拒否反応を招きがちです。一方、購入直後には関連商品の案内が響きやすいこともあります。顧客の状況と心理に合わせて「今か、待つべきか」を丁寧に見極めます。
関連性と価値を明確にする
クロスセルは現行商品と組み合わせることで便利さや効果が増すものを、アップセルは上位版の明確な利点を、具体的な成果とともに示します。高額品の一方的な押し上げではなく、課題解決や体験向上という文脈で価値を語ることが肝心です。「自分のことを分かってくれている」という安心が心理的ハードルを下げます。
負担の小さな提案から始め、小さなYesを重ねる
提案される側の心理的ハードルへの配慮も欠かせません。人は、いきなり大きな変化や負担を求められると警戒するものです。まずは「少しの追加料金で、こんなメリットがあります」と、気軽に検討できる提案を心がけましょう。マクドナルドでポテトを薦めるように、顧客が抵抗なく受け入れられる小さな成功体験を積んでもらうことが、将来の大きな提案 (アップセル) への布石にもなります。
ダウンセルで、種をまく
断られた時や断られ方にも、営業力が問われます。上位提案が刺さらないときの受け皿がダウンセルです。機能を絞ったプランや短期トライアルは、関係を途絶させず、将来的なクロスセル・アップセルへの布石となります。いったん小さく始めても、成果が見えれば後から拡張できます。離脱を防ぎ、LTVを守る設計です。
売って終わりにしない
クロスセルやアップセルは売って終わりではなく、その後のフォローが肝心です。購入後のサポートなどで、顧客満足度を維持向上させましょう。長期的な信頼関係を築き、顧客が新たな課題に直面した際に「まず御社に相談しよう」と考えてもらえるようになります。信頼残高を積み上げていくことは、結果的にクロスセル・アップセルの成功率を高める近道です。
常に「顧客の立場に立った提案か」を自問しながら設計と運用を回していけば、収益だけでなく顧客価値も高まります。結果として、企業と顧客の双方にとってメリットのあるクロスセル・アップセル・ダウンセルが実現します。
顧客を中心に据えない提案は、信頼を損なう
反対に、顧客の状況に合っていなければ逆効果になりえます。クロスセル・アップセル・ダウンセルは本来「顧客のため」の提案ですが、使い方を誤ると強引な売りこみの印象を与え、せっかく築いた信頼を損ねてしまうリスクがあります。ここでは、ありがちな失敗例を紹介します。
文脈やタイミングを無視したクロスセル
クロスセルで避けるべきは、顧客のニーズや文脈と無関係な商品を提案してしまうことです。例えば、予算や低価格を重視している顧客に高価なオプションを矢継ぎ早に勧めたり、ソフトウェアの導入目的とは全く関係のない別のサービスを提案したりするケースです。文脈を無視すると、顧客には不自然さが残り、信頼よりも売り込み感が強く印象に残ってしまいます。顧客が「自分に合わせた提案だ」と感じられるよう、ニーズと文脈への配慮が不可欠です。
価値を十分に伝える前のアップセル
アップセルでありがちな失敗は、顧客がまだ成果や満足を期待・実感していない段階で、上位プランや高額商品を提案してしまうことです。アップセルは“さらなる価値”を提供する提案であり、基本的な価値を理解・体感してもらった後に行う方が効果的です。タイミングを誤ると、提案は逆効果になり、押し売りの印象を与えかねません。
売り込み感が前面に出た唐突なダウンセル
ダウンセルは本来、予算や条件のハードルで迷っている顧客への代替提案です。しかし、先に高額な商品やサービスを提示した直後に安価な案を出すと、「最初は高いものを売りつけようとしたのでは」と疑念を抱くことがあります。有効なダウンセルにするためには、「お客様のニーズや状況を踏まえると、こちらが最適です」という姿勢や文脈の中で提示することが重要です。
投下リソースの費用対効果
注意すべきは業務効率とのバランスです。顧客数や分析の深さ、営業組織のケイパビリティによっても異なりますが、特定顧客に対して過度な分析やカスタマイズ提案を行うと、単一顧客の売上には貢献しても、営業カバレッジの低下などにより、結果的に組織全体の売上低下につながるおそれがあります。
これを防ぐには、顧客のニーズや特徴を類型化し、その知見を営業チーム全体で共有することが有効です。誰もが適切なタイミングで適切な提案ができる状態を作ることで、仕組み導入の費用対効果を高められます。こうしたリソースの偏りは、クロスセルに限らず新しい取り組み全般で起こりがちなため、事前に実行体制を整えることが重要です。
「押し売り感」の心理学
顧客が営業提案に対して「押し売りされている」と感じるのは、必ずしも提案が強引だからではありません。多くの場合、提案内容が顧客の状況や物語 (ナラティブ) に寄り添っていないときに生じます。
人は誰しも、自分の課題解決のストーリーを描きながら商品やサービスを検討しています。たとえば「在宅勤務を快適にしたい」と考えている顧客に、まったく脈絡のない商品を勧めれば、違和感を覚え「なぜこの営業はこんなものを売ろうとするのだろう?」と警戒されてしまいます。その瞬間、提案の意図が顧客の課題解決ではなく“自社の売上”であることを見抜かれ、信頼は崩れます。
効果的なクロスセル・アップセル・ダウンセルとは、顧客の物語に寄り添い、その続きをより良い方向へ導く提案です。顧客の課題を深く理解し、その解決策として自然に受け入れられる形で提示すれば、「押し売り」にはなりません。裏を返せば、「この提案は誰のためのものか?」という問いを常に行い、答えが“自社のため”になっていないかを確認すること。それが、信頼を損なわない営業の基本姿勢です。
クロスセル営業を有効活用するために
クロスセルは単なる販売テクニックではなく、顧客中心主義を体現する手法の一つです。近年、テクノロジーの進化により、顧客データ分析やパーソナライズド提案はかつてないほど容易になりました。これにより、クロスセル戦略を実行するための土台は整いつつあります。しかし、その成果を最大化するには、営業戦略と組織体制の両輪が欠かせません。
具体的には、現場の営業スキル向上に加え、部門横断で顧客情報を共有する仕組みづくり、提案効果を定量的に測定しPDCAを回すマネジメント体制が必要です。こうした全社的な連携と改善が、継続的な売上成長と顧客満足を両立させます。
さらなる企業成長のためには営業戦略と経営管理体制の構築が必要です。データドリブンかつ顧客本位の営業力強化にご関心がございましたら、ぜひグランド・デザイニング・グループにご相談ください。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
まずは無料相談してみる▼「GDGマガジン」とは?
GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かし、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。
監修者

宇納 陽一郎
グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営・営業・管理の実体験を活かした営業戦略や経営経営管理体制の構築支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。
※本サイトの情報は、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、最新情報の確認や個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。
関連記事
 マガジンTOP
マガジンTOP


